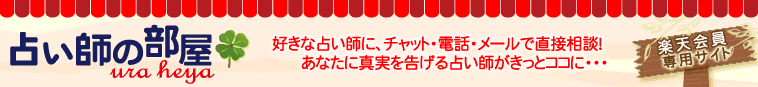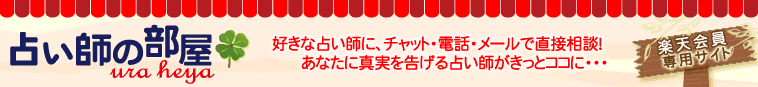2024年1月16日更新
占いには、専門用語がたくさん! 知りたかったあの用語、この用語を解説します。
ら行
ライオンズゲート
/
羅盤
/
六曜
/
リリス
/
ルネーション・サイクル
/
六十干支
/
魯班尺
【ライオンズゲート(lion's gate)】:その他
|
ニューエイジ系、スピリチュアル系の人々が、立秋のことをライオンズゲートと呼ぶことがあります。詳細は
ゲートを見てください。
羅経盤(らぎょうばん)、風水羅盤(ふうすいらばん)とも。中央に方位磁針が埋め込まれた円盤で、バウムクーヘンのように何層にも同心円が描かれ、各円には、十二支、八卦、二十四宿など、さまざまな種類の方位を示す要素が並んでいます。
北斗七星が描かれた天文占の道具、式盤(しきばん・ちょくばん)を原型として、大地の万象を占うものとして作られました。歴史上、式盤が登場するのは、三国志でおなじみの後漢の時代(紀元1世紀から2世紀ごろ)。その後、時代が下るにつれて、羅盤にはたくさんの要素が付け足されていき、現在では36層にもなりました。流派によって少しずつ内容が違い、その中でもポピュラーなのが、三元羅盤と三合羅盤の2種類です。
風水師は、占いたい場所の中央に羅盤を置き、磁石で方位を合わせて、吉凶を判断します。
日本で人気のある暦注(れきちゅう)のひとつ。以下、6種類の星が、新月の瞬間を含む日を始まりとして、1日交代でにめぐります。
| 六曜 | 読み方 | 古い名前の例 |
| 先勝 | せんかち・さきかち・せんしょう | 速喜 |
| 友引 | ともびき・ゆういん | 留連 |
| 先負 | せんまけ・せんぷ・せんぶ・さきまけ | 小吉 |
| 仏滅 | ぶつめつ | 空亡 |
| 大安 | たいあん・だいあん | 泰安 |
| 赤口 | しゃっこう・しゃっく・じゃっく・じゃっこう・せきぐち | 赤口 |
三国志演義の人気者・諸葛孔明が考えたなどという俗説もありますが、実際には、もっと後の時代になって作られたもののようです。
中国で時刻の吉凶を占った「小六壬(しょうりくじん)」で使われていた用語が、鎌倉時代から室町時代ごろ、日本に渡り、独自の解釈がつけられていきました。時代を経るうちに6つの星の名前も、めぐる順番も変化し、現在の形に落ち着いたのは、19世紀の初めであるようです。
明治の初めに、日本政府が太陽暦を採用した折には、迷信として切り捨てられました。しかし、大安・仏滅といった言葉は大変わかりやすく、吉凶をはっきりイメージしやすいせいか、普段は占いを気にしない人でさえ、縁起を担いで大安の日を選んで結婚式をあげたりします。
リリトと表記することもあります。非常に古くから占星術に取り入れられているのですが、謎が多い不思議な存在です。ダークムーン、ブラックムーン、闇の月などとも呼ばれています。
神話的な出自も古く、紀元前1300年ごろにまとめられた「ギルガメシュ叙事詩」に登場する女の悪魔が原型であるという説もあります。時代が下るにつれ、悪夢をもたらす夜の女神(夢魔)、吸血鬼、子どもをさらう鬼女など、さまざまなキャラクター性がつけ加えられていきました。
中でも極めつけは、「アダムの最初の妻」というストーリーです。誰もが知っている、「創世記」のアダムとイブのカップル。そのアダムには、以前、リリスという妻がいた。しかし、リリスは男性と同じ権利を与えてもらえなかったので、自由を求めて出奔した……のだとか。
謎が多いのは、神話的な面ばかりではありません。天文学的にも、リリスと呼ばれるものは何種類かあります。
まずは、「見えない月」。夜空に浮かぶ月の他に、もうひとつ、未知なる闇の月があるという説です。地球には月以外の衛星があるけれど、まだ発見されていない、という考え。とはいえ、発見されていないわけですから、その天体の位置を観測することはできず、ホロスコープ上に置くことができないので、占いには使えません。
続いてが、地球と月の重力が釣り合う、ラグランジュ・ポイント。月が地球の周りをまわる軌道には、5か所、重力が安定して、星屑が寄せ集まる点があります。そこに、星屑がたまっていって、なにやら天体らしきものが形成される……それがダークムーン・リリスであるという説。しかし、これをホロスコープ上に置く例は、ありません。
一般的な西洋占星術で使用するのは、月の遠地点(apogee・アポジー)です。「今年最大の満月ですね」「今年いちばん小さな満月です」などとニュースになるように、月の見かけの大きさはかなり変化します。これは、月と地球の距離が近づいたり離れたりするからです。いちばん近いときと遠いときとでは、なんと1割程度もの差が生まれます。
「月が地球から遠ざかり、奔放かつ自由になる点に、闇の女王・ダークムーン・リリスがいる」と定義されるのです。ミステリアスで、ぐっと惹きこまれる、魔力を感じるストーリーですね。
そんなところから、リリスは、月の闇の部分、無意識に求める自由、欲望、奔放なセクシャリティなどを表します。
「lilith horoscope calculator」などで検索すると、生まれたときにリリス(月の遠地点)がホロスコープ上のどこにあったか、計算できるページが見つかるでしょう。リリスは、約119日で黄道座標を1周します。
■出生時のリリスの星座で占う■
| リリスの星座 | 抗いがたい隠れた衝動 |
| おひつじ座 | 力づくで愛を奪い取りたい。 |
| おうし座 | 全身で快楽を感じたい。 |
| ふたご座 | すべてのことが知りたい。 |
| かに座 | 命がけで愛する者を守りたい。 |
| しし座 | すべての人に注目されたい。 |
| おとめ座 | 職務に忠実でありたい。 |
| てんびん座 | 最も美しい人になりたい。 |
| さそり座 | 愛のために死にたい。 |
| いて座 | できるだけ遠くへ行きたい。 |
| やぎ座 | 完璧な指導者でありたい。 |
| みずがめ座 | 自由でありたい。 |
| うお座 | 愛を信じたい。 |
※この他、火星と木星の間にある小惑星帯に「Lilith」という名の小惑星があります。しかしこれは、「もうひとつの月」「ダークムーン」としてのリリスとは関係なく名付けられたので、本項では扱いませんでした。
【ルネーション・サイクル(lunation cycle)】:西洋占星術
|
ルネーション・サイクルとは、月の満ち欠けのサイクルのこと。パリ生まれの音楽家兼占星術家、ディーン・ルディアの提唱した、「ルネーション占星術」の基本的な考え方です。
ルディアは、新月から次の新月に至る月の形を、まず、4つのグループに分けました。新月、上弦、満月、下弦です。
さらに4つのグループを2つに分割し、8つのグループにしました。ニュームーン、クレセントムーン、ファーストクォーター、ギバウスムーン、フルムーン、ディセミネイティングムーン、サードクォーター、バルサミックムーンです。
また、新月から次の新月までの月を月齢0から、月齢29の30種類に分け、8つのグループに割り振りました。
| 4グループ | 8グループ | 月齢 |
| 新月 |
ニュームーン | 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| クレセントムーン | 4 |
| 5 |
| 6 |
| 上弦 |
ファーストクォーター | 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| ギバウスムーン | 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 満月 |
フルムーン | 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| ディセミネイティングムーン | 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 下弦 |
サードクォーター | 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| バルサミックムーン | 27 |
| 28 |
| 29 |
生まれた日の月が、8つのグループのうちどれに属するかによって、その人のキャラクターが決まります。
■生まれた日の8グループで性格を占う
1:ニュームーン
ピュアで、行動力に満ちた人。
2:クレセントムーン
好奇心旺盛で、チャレンジ精神を持った人。
3:ファーストクォーター
困難に立ち向かう、エネルギッシュな人。
4:ギバウスムーン
センスがよく、バランス感覚に優れた人。
5:フルムーン
存在感があり、周囲に強い影響を及ぼす人。
6:ディセミネイティングムーン
能力が高く、与える喜びを知っている人。
7:サードクォーター
社会性が高く、アイディアに満ちた人。
8:バルサミックムーン
ロマンチストで、神秘的な直感力を持った人。
以下の手順で、生まれたときの月の形を調べると、あなたのルネーション・サイクルの月齢がわかります。
1:生まれた日の旧暦の日付を調べる。
「旧暦 XXXX年(生まれた西暦年)」で検索すると、旧暦何日に生まれたかわかります。
2:旧暦の日付から、1引く。
旧暦は、新月の瞬間を含む日が必ずついたちです。旧暦の日付からマイナス1すると、ルネーション・サイクルの月齢が出ます。
例:1980年5月15日生まれの人
旧暦を調べると、4月2日。
2−1=1
ルネーション・サイクルの月齢は1。
ニュームーンのグループ。
【六十干支(ろくじゅっかんし)】:四柱推命/九星・気学/風水/算命学/易
|
十干と十二支を組み合わせたもの。10個の干と12個の支を順番に並べると、甲子、乙丑、丙寅……癸亥までの60種類になります。これを使って、60の周期で、年・月・日・時(刻)を数える方法は、すでに殷(いん)の時代には始まっていたようです。他にも、角度や方位を表す「単位」としても使われます。やがて、これが占いにも利用されるようになり、陰陽五行説に基づいて、解釈がつけられていきました。
風水で占うとき、方位に吉凶があるように、長さにも吉凶があります。魯班尺は、門、梁、間口、家具など、あらゆるものの寸法を測る定規です。紀元前5世紀、魯の国の天才建築家・魯班が発明したと言われています。
魯班が作ったときは、L字型の曲尺だったようですが、時代が下るにつれて、普通の物差しのような形や、巻き尺タイプのものも生まれました。
風水師はこれで建物の寸法を測り、吉凶を判断します。とくに重要視されるのは、門戸の寸法です。また、同じ長さ・高さでも、場所や対象物、その部屋を日常的に使う人物によって、吉凶の判断が違います。