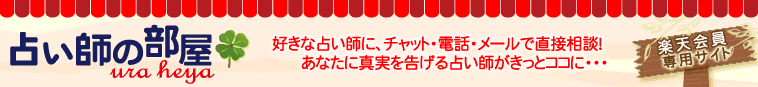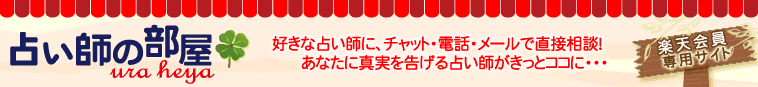2025年6月16日更新
占いには、専門用語がたくさん! 知りたかったあの用語、この用語を解説します。
さ行
歳差
/
サビアン占星術
/
三才
/
サンサイン占星術
/
十二運
/
十二支
/
十干
/
秋分
/
守護星
/
春分
/
小惑星
/
シンギングボウル
/
スーパームーン
/
節分
/
相生・相剋・比和
西洋占星術とインド占星術の違いを説明するとき、真っ先に問題になるのが、『歳差(さいさ)』です。両占星術とも、【おひつじ座】から【うお座】までの12星座が登場するのですが、意味するところが違います。
占いファンの人の中には、西洋占星術では【おひつじ座】生まれだけど、インド占星術では【うお座】生まれといったことが起きるのを体験している人も多いことでしょう。
この違いが生まれる原因が、歳差です。インド占星術の用語では、アヤナムシャといいます。
【おひつじ座】から【うお座】までの12の星座名は、太陽の通り道・黄道につけられた目盛りです。黄道は、全天360度をぐるりととりまいています。その360度を30度ずつ12に等分割して、最初の30度に【おひつじ座】、次の30度に【おうし座】……と、順に名づけたのが黄道12星座です。
ここまでは、西洋占星術もインド占星術も同じ。しかし、起点となる【おひつじ座】の0度の定義が違うので、両占星術には、ずれが生じます。そして、そのずれは今こうしている間にも、じわじわと広がっています。
西洋占星術は、春分点を【おひつじ座】の0度と定義します。今から2000年くらい前、春分点は、空に描かれた星座のおひつじ座のあたりにありました。けれど、現在の春分点は、空に描かれた星座のうお座のあたりにあります。
春分点が動いている……? それこそが、『歳差』の仕業です。地球は、太陽の周りを公転していますが、太陽系を外側から見ると、少し斜めに傾いています。赤道をまっすぐ太陽のほうに向けているのではなく、23.4度ほどの傾きがあります。その傾きが、長い時間が経過するうちに、円を描いて揺れるのです。ちょうど、回っているコマが、ゆらゆらと頭を振るように。
この「ゆらゆら」が、歳差運動です。地球が歳差運動をするのは、太陽や月、その他の惑星の引力に干渉されるから。そのせいで、春分点が移動していきます。こうして、長い時間が経つ間に、西洋占星術の【おひつじ座】は、空に描かれる星座のおひつじ座からずれて、今は、空に描かれる星座のうお座のあたりの領域を示すこととなりました。
一方、インド占星術は、春分点ではなく、空に描かれる星座を基準にしています。インド占星術は、占いで使う星座の領域と、空に描かれている星座の領域が一致しているのです。
だから、これからも、西洋占星術の【おひつじ座】と、インド占星術の【おひつじ座】の差は、広がる一方。26000年くらい経つと、歳差運動はぐるりと一周して、西洋占星術の【おひつじ座】が、インド占星術の【おひつじ座】の位置に、戻ってくるときがやってきます。
【サビアン占星術(sabian astrology)】:西洋占星術
|
黄道座標360度の1度ずつに、神秘的な物語とシンボルを割り振った占星術です。伝統的な西洋占星術では、黄道座標を12に分割して、12星座を設定し、12パターンのシンボルを割り振りますが、サビアンでは360パターンのシンボルが設定されています。
古典の占星術で「太陽が〇座にあるときに生まれた人は……」と読んでいくのと同様に、「太陽が〇座〇度にあるときに生まれた人は……」と、解釈をつけていきます。主要10惑星について、ひとつずつサビアンのシンボルを探るだけでも、楽しいものです。
また、各惑星が位置する度数のシンボルだけでなく、1度前の度数のシンボル、反対側(オポジション)にある度数のシンボルなども組み合わせて解釈すると、物語性がぐっと深くなります。その神秘的な物語展開に魅了され、サビアン・ファンになる人たちも多くいることでしょう。
日本でサビアン占星術が知られるきっかけのひとつとなった、松村潔著『神秘のサビアン占星術』から例を引用すると……
「牡羊座1度:海から上がったばかりの女性を、アザラシが抱いている。」
「牡牛座3度:開花した三つ葉の芝に自然な歩みで入り込む。」
「蟹座30度:アメリカ革命の娘。」
「魚座10度:飛行機が、大地を覆う雲の中を飛びつづける。」
このように、「アメリカ革命」「飛行機」といった、古代の占星術とはおよそつながりがない単語も出てきます。
サビアン占星術は、占星術の歴史の中では新しい技法で、1925年に、アメリカの占星術師マーク・エドモンド・ジョーンズと、チャネラーのエルシー・ウィラーによって設計されました。ジョーンズは、1から360までの数字を振った360枚の紙を用意し、1枚ずつ白紙の面をウィラーに見せて、どんなビジョンが浮かんだか聞き取り、書き取りました。そして、ウィラーのビジョンを端的なフレーズにまとめました。
その後、フランスの占星術師であり、音楽家でもあるディーン・ルディアが、ジョーンズとウィラーの新しい占星術に着眼し、360度それぞれのシンボルをさらに深めていきました。ルディアは、ジョーンズの著した各度数のフレーズを改訂して、さらに洗練されたフレーズを紡ぎ出しました。
他にも、ルディアのように、改訂版のフレーズを作った占星術師は現れましたが、その内容はあまり定着しませんでした。
現在では、ジョーンズによるオリジナル版『Sabian Symbols in Astrology』に記されたフレーズの他、ルディアによる改訂版と、その改訂版をルディア自身がさらに改訂した版の3種類が主流になっています。
|
【三才(さんさい)】:四柱推命/九星・気学/風水/算命学/易など
|
中国発祥の世界観のひとつ。世界を構成する天・地・人の3つの気を総称して三才(さんさい)と言います。三元(さんげん)、三儀(さんぎ)、三極(さんきょく)とも。解釈の仕方は学派によって少しずつ違いますが、天は陽で父、地は陰で母、人はその間に生まれた子と考えるとわかりやすいでしょう。生け花などの芸術の世界で、黄金比率の三角形として表現されることもあります。政治や軍略の原理として使われるときは、「天の機、地の利、人の和」が揃うのが最上とされます。易、四柱推命、九星気学、風水など、東洋の占いすべてに共通する世界観です。
【サンサイン占星術(sun sign astrology)】:西洋占星術
|
雑誌やWEBの記事にある、12星座別の占いのこと。sun sign astrology、すなわち、太陽の星座の占星術です。
サンサイン占星術の基準は、出生時の太陽の位置です。
天文学的に表現すると、あなたが生まれた瞬間、太陽が黄道12星座のうち、何座の方向にあったか。これを確定することで占いをスタートします。
黄道12星座とは、おなじみのおひつじ座からうお座までの12の星座。占星術では、太陽の通り道である黄道を、12の星座の領域に分割します。
たとえば、「おひつじ座生まれ」というのは、太陽が黄道上のおひつじ座の領域にあるときに生まれたことを示します。
※注:ここでいう「おひつじ座」は、天空に描かれた星座のおひつじ座とは違います。詳しくは、
歳差、
へびつかい座の項目をごらんください。
黄道は全天360度に描かれた円で、各星座の領域は30度ずつ。春分点をおひつじ座の0度として、30度進むとおうし座0度、さらに30度進むとふたご座0度……というふうに表します。
太陽が星座の境界をまたぐのは、一瞬のことなので、誕生日は同じでも生まれ星座が違うということが起こりえます。たとえば、双子の一方が、太陽がおひつじ座ギリギリの位置を運行中のときに生まれ、もう一方がその少しあと、太陽がおうし座に入ってから生まれたならば、双子でも生まれ星座は別ということになります。
雑誌やWEBの記事では「おひつじ座:3月XX日から4月XX日生まれの人」と表記されていることがあります。この「XX日」の部分が、記事によって違うので、混乱していた人もいるでしょう。記事を掲載するスペースに制限がある雑誌などの媒体では、「太陽が星座の境界をまたぐ瞬間を含む日付」を掲載するのが限界です。
また、地球は厳密に正円を描いて太陽の周りを公転しているわけではないし、ぴったり365日で一周しているわけでもありませんから、太陽が星座の瞬間をまたぐ瞬間を含む日付は、年によって前後します。
厳密に占うのであれば、出生の瞬間の太陽の位置を正確に測らなければなりません。太陽が星座の境界線を越えるころに生まれた人は、ホロスコープ計算アプリで、正確な太陽の星座を出してください。そしてこれからは、記事に掲載されている日程を無視して、本来の太陽の星座の項目を読みましょう。
ところで、雑誌などでおなじみの「〇月の星占い」といった、12星座別の占いコラムが最初に書かれたのは、いつごろだったのか。
それは1930年、イギリスの新聞「サンデー・エクスプレス」だといわれています。執筆者は、占星術師リチャード・ハロルド・ネイラーです。
イギリス王室のマーガレット王女のホロスコープを読む記事の下に付け加えられた、短いコラム。一般の人に向けた「誕生日ごとの占い」が、いわゆる星座占いの記事の原型となりました。「〇月〇日から×月×日までに生まれた人には、こんなことが起きるでしょう」といったことを書いた記事でした。それが大いに人気を博します。
そこでネイラーは、サンサイン占星術のシステムを「あなたの星(Your stars)」と名付けて、占い記事を連載しました。その後、多くの新聞が占星術師たちに記事の執筆を依頼し、星占いの記事は世界中に広まって、現在に至っています。
占星術を一般に広める、大きな役割を果たしたのが、サンサイン占星術。それはライト感覚の読み物でありながら、実は、天空で最も光り輝く星・太陽を基準にした、由緒正しい占いでもあるのです。
「十二運星(じゅうにうんせい)」とも。算命学の「十二大従星(じゅうにだいじゅうせい)」とも対応しています。
その人が持つエネルギーの強弱を示すと言われます。しかし、強いから良い、弱いから悪いというわけではありません。生まれ持つエネルギー量を知り、環境や場面に合わせてコントロールするのが重要と考えます。
十二運の種類、強度、意味を表にまとめると以下のようになります。古代中国の男子の一生を段階ごとに追うのが、十二運の本来の意味でした。
| 十二運 | 読み | 強度 | 意味 |
| 胎 | たい | 中 | 母の胎内に入る。 |
| 養 | よう | 中 | 胎内で養われる。 |
| 長生 | ちょうせい | 強 | 外界に誕生する。 |
| 沐浴 | もくよく | 中 | 産湯をつかう。 |
| 冠帯 | かんたい | 強 | 元服する。 |
| 建禄 | けんろく | 強 | 名のある人物になる。 |
| 帝旺 | ていおう | 最強 | 人生の盛りを迎える。 |
| 衰 | すい | 弱 | 老いて衰える。 |
| 病 | びょう | 弱 | 病気になる。 |
| 死 | し | 弱 | 生命活動停止。 |
| 墓 | ぼ | 中 | 墓に入る。 |
| 絶 | ぜつ | 最弱 | 有から無に戻る。 |
四柱推命の命式の中には、以下の十二運が登場します。
1:日柱天干×各柱の地支で求める【十二運】
2:各柱天干×各柱の地支で求める【居る(いる)十二運】
3:各柱蔵干×各柱の地支で求める【座す(ざす)十二運】
流派によって差はありますが、一般的に「十二運」というと、「日柱天干×各柱の地支で求める十二運」のことを指します。
とくに日柱の十二運は、その人のパーソナリティも表す主要な十二運です。
十二運は、10の干と12の支を組み合わせた
六十干支(ろくじゅっかんし)と対応しています。
「生まれた日・干支」といったワードで検索し、あなたの誕生日の六十干支を調べると、下の表から「日柱の十二運」を求めることができます。
| ↓干×支→ | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 甲 | 沐浴 | 冠帯 | 建禄 | 帝旺 | 衰 | 病 | 死 | 墓 | 絶 | 胎 | 養 | 長生 |
| 乙 | 病 | 衰 | 帝旺 | 建禄 | 冠帯 | 沐浴 | 長生 | 養 | 胎 | 絶 | 墓 | 死 |
| 丙or戊 | 胎 | 養 | 長生 | 沐浴 | 冠帯 | 建禄 | 帝旺 | 衰 | 病 | 死 | 墓 | 絶 |
| 丁or己 | 絶 | 墓 | 死 | 病 | 衰 | 帝旺 | 建禄 | 冠帯 | 沐浴 | 長生 | 養 | 胎 |
| 庚 | 死 | 墓 | 絶 | 胎 | 養 | 長生 | 沐浴 | 冠帯 | 建禄 | 帝旺 | 衰 | 病 |
| 辛 | 長生 | 養 | 胎 | 絶 | 墓 | 死 | 病 | 衰 | 帝旺 | 建禄 | 冠帯 | 沐浴 |
| 壬 | 帝旺 | 衰 | 病 | 死 | 墓 | 絶 | 胎 | 養 | 長生 | 沐浴 | 冠帯 | 建禄 |
| 癸 | 建禄 | 冠帯 | 沐浴 | 長生 | 養 | 胎 | 絶 | 墓 | 死 | 病 | 衰 | 帝旺 |
|
【十二支(じゅうにし)】:四柱推命/九星・気学/風水/算命学/易など
|
東洋の占いでは、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥(ね・うし・とら・う・たつ・み・うま・ひつじ・さる・とり・いぬ・い)の12個が、1年ごと・1か月ごと・1日ごと・2時間ごとに順にめぐるルールを使って、運命を読み取ります。もともとは占いに使われていたものではなく、季節の流れや時間、方位などを表す「単位」でした。陰陽五行よりも古い時代に成立していたものであるらしく、いつ、誰が作ったのかわかりません。十二支を動物に当てはめるアイディアは、ずっと時代が下ってから生まれ、「十二生肖(じゅうにせいしょう)」ともいいます。
十二支の最もポピュラーな使い方の例は、いわゆる生まれ年。子年の生まれは頭の回転が速いとか、亥年生まれは素直でまっすぐだとか、聞いたことがある人も多いことでしょう。
これは、その人が生まれたときに、木星が天空のどの位置にあったかに由来しています。木星は、12年かけて天空を1周するので、十二支は12個ある……なにやら、占いファンにとっては、なじみのあるシステムですね。
そう、西洋占星術の「12星座」の中国版が、「十二支」なのです。そのため、英語では十二支のことをチャイニーズ・ゾディアック(Chinese zodiac)と言うことがあります。
とはいえ、12星座と十二支は、イコールで結べるわけではありません。
発想のもとは似ているのですが、地球上のどこか1か所でこのアイディアが生まれて、分化したわけでもなさそうです。もしかしたら、北半球の西と東で、別々の人たちが同時発生的に、同じアイディアをひらめいたのかも……? 同じ空の下で、同じ星空を見上げているのですから、似たような発想を得るのも自然なことですね。
東洋では、360度の天空を12個に区分するシステムを、方位を示す区分としても使いました。それは現代の私たちの生活にも根付いています。
たとえば、地図や地球儀に引かれた、子午線(しごせん)。子(真北)と午(真南)をつなぐ線だから、そう呼ばれます。
さらに身近なのは、午前・午後という言葉。これは、十二支の午(うま)が真南を意味することから来ています。太陽が南中する瞬間が、正午。それよりも前の時間が午前で、後の時間が午後というわけです。
※厳密にいうと、日本国内にも時差があり、季節によっても南中時間にずれがあるので、私たちが使っている時計の12時ぴったりに太陽が南中するとは限りません。
なお、正午を中心に、前後1時間ずつ、合わせて2時間の時間帯を「午の刻(うまのこく)」といいます。1日は24時間なので、十二支は2時間ずつの時間帯に割り振られています。
■十二支と、方角・時間帯の対応■
| | 十二支 | 方角 | 時間帯 |
| 1 | 子 | 北 | 23時から01時 |
| 2 | 丑 | 北北東 | 01時から03時 |
| 3 | 寅 | 東北東 | 03時から05時 |
| 4 | 卯 | 東 | 05時から07時 |
| 5 | 辰 | 東南東 | 07時から09時 |
| 6 | 巳 | 南南東 | 09時から11時 |
| 7 | 午 | 南 | 11時から13時 |
| 8 | 未 | 南南西 | 13時から15時 |
| 9 | 申 | 西南西 | 15時から17時 |
| 10 | 酉 | 西 | 17時から19時 |
| 11 | 戌 | 西北西 | 19時から21時 |
| 12 | 亥 | 北北西 | 21時から23時 |
最後に、ちょっと便利なトリビアを。
生まれ年の十二支を電卓で計算する方法をご紹介しましょう。
西暦4桁の12で割り切れる数の年は、申年です。12で割って1余ると酉年、2余ると戌年、3余ると亥年、4余ると子年……11余ると未年、となります。
電卓に、調べたい年の西暦を入力して、12で割りましょう。
小数点以下の数字なしで割り切れたら、その年は申年。
小数点以下の数字が出たらそれを切り捨てて、小数点以上の数字に12を掛けます。
こうして求めた4桁の数字は、調べたい年の直前の申年です。
調べたい年の4桁から、申年の4桁を引いてください。
申年の1年後は酉年、申年の2年後は戌年、申年の3年後は亥年、申年の4年後は子年……申年の11年後は未年、と数えると、その年の十二支が出ます。
※ただし、立春(2月4日ごろ)より前に生まれた人は、前の年の生まれとみなします。
例:1987年の十二支は?
1:電卓に1987を入力して12で割ると、165.58333...。
2:小数点以下を無視すると、165。
3:165×12=1980 直前の申年は1980年。
4:1987-1980=7 調べたい年は申年の7年後。
5:申年の7年後は卯年。1987年は卯年。
|
【十干(じゅっかん・じっかん)】:四柱推命/九星・気学/風水/算命学/易
|
木・火・土・金・水の五行にそれぞれ陰陽を組み合せて、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸(きのえ・きのと・ひのえ・ひのと・つちのえ・つちのと・かのえ・かのと・みずのえ・みずのと)の、10の気としたもの。名前の最後に「え」とつくと陽、「と」とつくと陰です。甲に始まり、癸に至り、また甲に戻る様子は、万物の栄枯盛衰の循環を現しています。十二支と同様、1年ごと・1か月ごと・1日ごと・2時間ごとに順にめぐるルールを使って、運命を読み取ります。
【秋分(autumnal equinox)】:その他
|
太陽が秋分点(天秤座00度00分)に到達した瞬間。春分のちょうど反対側にあたります。でも厳密には、春分の瞬間のぴったり半年後に、太陽が秋分点に到達するわけではありません。天文的には、地球が太陽の周りを公転する軌道、地球の自転の傾き、月の引力による影響、金星など他の天体の影響など、複雑な条件が関わります。そのため、私たちが日常で使う時計が示す「時間」を基準にすると、ズレが生じるのです(国立天文台のHP「春分の日・秋分の日」を参照)。
春分から秋分までの「時間」は、約186日。どれほどのズレが生じるのか、10年分のデータを比較してみましょう。
| 春分の瞬間 | 秋分の瞬間 | 春分から秋分までの時間 |
| 2024年3月20日12:07 | 2024年9月22日21:44 | 186日と9時間37分 |
| 2025年3月20日18:02 | 2025年9月23日03:20 | 186日と9時間18分 |
| 2026年3月20日23:46 | 2026年9月23日09:06 | 186日と9時間20分 |
| 2027年3月21日05:25 | 2027年9月23日15:02 | 186日と9時間37分 |
| 2028年3月20日11:18 | 2028年9月22日20:46 | 186日と9時間28分 |
| 2029年3月20日17:02 | 2029年9月23日02:39 | 186日と9時間37分 |
| 2030年3月20日22:53 | 2030年9月23日08:27 | 186日と9時間34分 |
| 2031年3月21日04:41 | 2031年9月23日14:16 | 186日と9時間35分 |
| 2032年3月20日10:22 | 2032年9月22日20:11 | 186日と9時間49分 |
| 2033年3月20日16:23 | 2033年9月23日01:52 | 186日と9時間29分 |
※太陽が牡羊座00度(春分)と天秤座00度(秋分)に到達した日時はASTOSEEKで計算しました。国立天文台の発表とは1、2分程度ズレる場合があります。
こうしてみると、時間数が法則性もなくゆらゆら揺れているのがわかります。サンプルとして抽出した10年間で、いちばん短い2025年と、いちばん長い2032年とでは、31分も差があります。
天体の動きには揺らぎがあるということがわかって、興味深いですね。
天文的な特徴については、春分の項目にも記したので、併せて参照してください。
さて、もう少し日常に目を向けて、私たちが使うカレンダーの秋分についてお話ししましょう。
「秋分の日」とは、秋分の瞬間を含む日です。ある年の秋分の日は、その前年の2月1日、官報に「暦要項(れきようこう)」が掲載されることによって、正式決定となります。
少し古いカレンダーである旧暦では、新月から次の新月までの間に秋分を含む月を八月と定めました。
歴史上においては、秋分は秋の始まりを表す日として、重要視されてきました。
北半球では、秋の実りを祝うときとして、さまざまな祭りが開かれます。
ワインやビールなど、酒の醸造にまつわる祭りがあるのも、秋ならではといえるでしょう。
日本では、京都の晴明神社で秋分の日に「晴明祭」が行われます。
晴明神社は、陰陽師・安倍晴明をまつる神社です。秋分の日の前夜から2日間にわたって、伝統的な儀式が執り行われます。
【守護星(ruler)】:西洋占星術/インド占星術
|
星座には、それぞれに守護星(支配星とも)があります。守護星になるのは、
惑星たちです。各星座にも固有の意味があるのですが、守護星はその星座に動機を与えます。
堅実な性質と言われる星座、おうし座とやぎ座を例にとりましょう。どちらもしっかりたくわえを作り、少々困った事態に追いこまれても、耐え抜く力があります。
しかし、両星座では、たくわえを作る動機が違います。ここで関わってくるのが、守護星です。
おうし座の守護星は愛と美の女神の星、金星。美しいもの、おいしいもの、心地よいものに囲まれて、豊かな暮らしがしたい。だから、がんばって貯金します。
一方、やぎ座の守護星は思慮深い老賢者の星、土星です。いつも不測の事態に備え、問題に対処できるよう、二重にも三重にも守りを固めています。貯金は、そんな守備行動のひとつです。
このように、守護星は、その星座の「求めるもの」に影響を与えます。
■各星座の守護星■
| 星座 | 守護星 | 星の性質 | 動機 |
| おひつじ座 | 火星 | 戦いの星 | 道なきところを開拓したい |
| おうし座 | 金星 | 愛と美の星 | 美しいものに囲まれて心地よく過ごしたい |
| ふたご座 | 水星 | コミュニケーションの星 | 多くの人と話し、情報を集めたい |
| かに座 | 月 | 母性と優しさの星 | 愛するものを守りたい |
| しし座 | 太陽 | 意志と目標意識の星 | 成功したい |
| おとめ座 | 水星 | コミュニケーションの星 | 多くの人と話し、情報を集めたい |
| てんびん座 | 金星 | 愛と美の星 | 美しいものに囲まれて心地よく過ごしたい |
| さそり座 | 火星
冥王星 | 戦いの星
深い情愛の星 | 道なきところを開拓したい
愛するものとひとつになりたい |
| いて座 | 木星 | 幸運と豊かさの星 | 物心ともに豊かになりたい |
| やぎ座 | 土星 | 思慮と堅実の星 | 実用性重視 |
| みずがめ座 | 土星
天王星 | 思慮と堅実の星
変革の星 | 実用性重視
自由でありたい |
| うお座 | 木星
海王星 | 幸運と豊かさの星
幻想の星 | 物心ともに豊かになりたい
夢を見ていたい |
さそり座、みずがめ座、うお座に2つの守護星があるのは、近代以降の天文学の影響によるものです。天王星、海王星、冥王星が発見されたのは、望遠鏡が発明されてからですから、紀元前の占星術師たちが知るはずもありません(いちばん早い天王星でも、1781年の発見)。古典の西洋占星術と、インド占星術に登場するのは、土星までの、肉眼で見える7つの星たちです。
各星座の守護星たちは、その星座に入った惑星たちにも影響を与えます。いわゆる「〇〇座生まれ」とは、太陽がその星座に入ったときに生まれたことを意味します。太陽は、その人のアイデンティティを決定する星です。
例えば、ふたご座の太陽は、守護星であるコミュニケーションの星、水星の影響を受けて、多くの人と対話し、情報を集めます。
地球から見る太陽の通り道・黄道と、地球の赤道を天球に投影した天の赤道、この2つの円は、23.4度ほどの傾きをもって交差しています。交差する点は、2つ。その一方を春分点、もう一方を秋分点と呼びます。赤道に対して黄道が南から北へ交わる方の点が、春分点。天文学では、春分点を黄道と天の赤道の始まりの点と定めています。
春分点は、誕生星座の牡羊座の始まりでもあるので、アリエス・ポイント(Aries point)とも呼ばれます。しかし今、天を見上げると、春分点は、ひつじの姿が描かれた「おひつじ座」の領域にはありません。
2000年ほど前には「おひつじ座」にあったのですが、現在は魚の姿が描かれた「うお座」の領域にあります。地球の歳差運動によって、春分点は少しずつずれていくからです。そのずれは、1年で約50秒、72年で約1度。360度1周してもとの位置に戻るには、約25800年かかります。
春分点は、太陽が春分の瞬間に位置する点でもあります。そして春分の日は、太陽が春分点に到達する瞬間を含む日です。時差がある日本とヨーロッパでは、カレンダー上の春分の日の日付が、1日違うということもありえます。日本では、毎年2月の初めの官報に、「暦要項」が掲載され、翌年の春分の日が発表されます。この発表までは、実は、正式な春分の日は、決まっていないのです。
春分の日といえば、太陽が真東から昇って、真西に沈む日。そして、昼夜の長さが等しくなると言われています。ところが、当日の日の出と日の入りの時間を調べてみると、昼のほうが長いことに気づきます。
たとえば、2024年の場合、春分の日は3月20日、日の出は5時45分、日の入りは17時53分です。太陽が5時45分に昇ったなら、そのぴったり12時間後の17時45分に沈むはずなのですが、実際には8分程度遅い時間に沈んでいます。
これには「日の出」と「日の入り」の定義が関係しています。日の入りは、太陽の上端が地平線上にふれた瞬間です。太陽の姿は全部見えないけれど、ほんの少し上端が顔を出した瞬間が、日の出。一方、日の入りは、太陽が完全に地平線下に隠れた瞬間です。
太陽の中心点が地平線と重なる瞬間を日の出、日の入りとするなら、昼夜の長さは同じなのでしょうが……。
天文的な日の出・日の入りの定義では、日の出のときに太陽半分、日の入りのときにもう半分、合わせて太陽1個分、昼の時間が長いことになります。
さらにもうひとつ、「大気差」という、地球の大気の効果も関連してきます。大気は、太陽光線を通すときに、レンズのような役割を果たして、実際には地平線の少し下にある太陽を、地平線上に浮かび上がらせて見せるのです。
大気差は、地平線に対して、0.5度くらい。これもまた、太陽1個分程度に相当します。
その結果、太陽が春分点に到達する瞬間を含む日・春分の日は、昼の時間が16分程度、夜の時間より長いことになります。私たちの時計で、昼と夜の長さが本当に等しくなるのは、春分の日より4、5日前です。2024年の場合は、3月16日と17日に、昼と夜の長さがだいたい同じになります。
天文学的には、惑星の定義を満たせない小さな天体、太陽系外縁天体、準惑星、彗星などを総称して「小惑星」と呼びます。現在観測されている小惑星の多くは、火星と木星の軌道の間にあるアステロイド・ベルト(小惑星帯)を公転しています。
「天体の光が地上に届いて、運命に影響を及ぼす」というのが西洋占星術の大前提ですから、天空を運行している小惑星たちも、私たちの運命に関与していると考えるのが自然でしょう。
とくに、4大小惑星と呼ばれるセレス(Ceres)、パラス(Pallas)、ジュノ(Juno)、ヴェスタ(Vesta)は、伝統的な占星術に登場する金星や火星などの惑星たちと、同じように重要であると考えられています。この4つは、1801年からの数年間に相次いで発見されました。実は、1930年発見の冥王星よりも、ずっと早くに見つかったのです。
4大小惑星は、ギリシア・ローマ神話の重要な女神たちです。
セレスは農業の女神デメテル、パラスは知恵と戦いの女神パラス・アテナ、ジュノは神々の王ゼウスの正妃ヘラ、ヴェスタはオリンピックの採火の儀式で有名なかまどの女神ヘスティア。占星術的解釈には、各女神の権能が反映されます。
女神たちの小惑星はアステロイド・ベルトにあり、公転周期はだいたい3年から4年。木星よりもずっと速く黄道12星座の中を移動しますから、個人的な運命に大きく関与すると考えられています。4大小惑星の表す意味を簡単にまとめてみましょう。
| 小惑星 | もたらす運命 |
| セレス | 子どもや作物を育てる。母性愛。 |
| パラス | 学問。女性の仕事と社会進出。 |
| ジュノ | 結婚。結婚後の女性の権利。 |
| ヴェスタ | 義務。守るべきもの。 |
この他にも、神々や女神たちの名前を持つ小惑星は無数にあります。
たとえば、ケンタウロス族の賢者ケイロンの小惑星、心の癒しをもたらすキロン(Chiron)は、4大小惑星に負けないくらい人気が高いかもしれません。心理占星術を扱う占星術師には、キロンを重視する人も多くいます。
ただ、小惑星はこの広い宇宙に無数に散らばっています。天体観測技術の発展により、次々と新しい小惑星が発見され、もうすでに80万個を越えました(2023年時点)。
見つかった小惑星には、国際天文学連合(IAU)が運営する小惑星センターによって、番号が振られます。
そのまま番号で呼ばれるのが大半ですが、既定の条件を満たせば、小惑星の発見者ではない一般の人でも、命名することができます。そして、その名前を国際天文学連合が認定すれば、正式な名前となります。
人名、地名、アイテムなど、本当に多種多様な名前がつけられています。自分や家族、大切な人の名前、ふるさとの地名を見つけることもあるでしょう。自身に関連する名を持つ小惑星が、ホロスコープの重要な位置にあるという例も、多く見受けられます。
海外の占星術サイトには、伝統的な惑星たちと並んで、小惑星たちのエフェメリス(運行表)を公開しているところもあります。普段見ているホロスコープに小惑星を追加すると、新鮮な発見があるでしょう。
【シンギングボウル(singing bowl)】:その他
|
シンギングボウルは、真鍮、銅、錫などの金属や、クリスタルで作られた、お椀型の楽器です。手のひらサイズのものから、直径40センチを超えるものまで、さまざまな大きさがあります。
起源は、チベット、ネパール、インド北部など、ヒマラヤの山岳地域。僧侶たちが儀式で使う法具です。
木製のスティックや、布を巻いたマレットで叩くと、ふくよかな音が広がります。その音が響いているうちに、スティックやマレットでボウルのふちをゆっくりなぞると、響きが増幅されて、豊かな倍音となり、音量もぐんと上がっていきます。
深みのある響きは耳に心地よく、リラクゼーション効果があるのだとか。また、音による振動を全身で感じることで、ストレス軽減、不眠改善、集中力アップなど、心身のバランスを整えるのに役立つともいわれています。
■シンギングボウルの種類
シンギングボウルには、大きく分けて、2種類があります。
★ヒマラヤ式・シンギングボウル
チベタン・ボウルともいいます。金属を叩いて、お椀型に整えたものです。チベット仏教の文字が彫られているデザインのものも多くあります。ヒマラヤ地域で伝統的に作られているものの流れを汲み、低音から高音まで、複雑な倍音を響かせます。
サイズの小さいものほど、擦って音を増幅させるのが難しいので、良い音を出すには練習が必要かもしれません。
★クリスタル・シンギングボウル
水晶を細かく砕き、高温で溶かして、ボウルの形に整形したもの。多くはフロスト加工されており、表面がすりガラス状にザラザラしています。このザラザラによって、マレットで擦ったときの音の広がりが大きくなるようです。
金属のシンギングボウルに比べて、透明感のある音が出ます。
■大きさ、音の響き、用途
シンギングボウルは、サイズが大きくなるほど、音程が低くなり、音量が大きくなります。小さなものは、高音域で、音量はそれほど大きくなりません。
大きさの違う複数のシンギングボウルを並べて、音階を作ることもできます。ただし、楽器として使うためには、正しく調律されている必要があります。
音階を、占星術の惑星やヨガのチャクラと対応させて、特定の音域の音を響かせ、運勢を活性化させるという使い方もあります。
小さなタイプのシンギングボウルをひとりで使う場合は、リラクゼーションのために鳴らします。ヨガや瞑想をするときに使う人も多いようです。静かに音を響かせ、振動に身を任せ、心を落ち着かせます。
また、大型のシンギングボウルを並べて、コンサートが開催されることもあります。ハンドベルのように、音階ごとに担当者を決めて、複数人で1曲を演奏する、大掛かりなステージも増えてきました。個人的なヒーリングシーンでの活用だけでなく、アートの世界でも注目される楽器です。
【スーパームーン(super moon)】:西洋占星術
|
ニュースなどでもたびたび話題にのぼる、スーパームーン。近年、大きくみえる満月を、このように呼ぶことが多くなりました。
でも、実は、天文学的な定義があるわけではありません。今のところ、その年の満月の中で、いちばん視直径が大きい満月をスーパームーンと呼ぶ、という慣例ができつつある、といったところでしょうか。
他にも、地球と月の距離が36万キロメートル以内で起きた満月を、スーパームーンと呼ぶこともあるようです。この場合は、1年間に複数回、スーパームーンの条件を満たす満月が起きる可能性がある、ということになります。
月と地球は、お互いの重力で引き合いながら回転しています。まるで、手をつないでダンスをしているかのよう。ふたつの天体は、等距離ではなく、近づいたり遠ざかったりしています。
月が地球にいちばん近づく点・近地点の付近で満月が起きると、満月はいつもより大きく見えます。
月が地球から最も遠い点・遠地点で起きる満月と、近地点で起きる満月では、視直径は14パーセント、明るさは30パーセントも違います。数字にすると、ずいぶん差がありますが、ふたつの満月を並べて見ることは不可能なので、その差を感じるのは難しいかもしれません。
なお、地平線近くに満月があると、地球の大気がレンズのような役割を果たして、月がとても大きく見えますが、これはまた別の話です。あくまでも、地球と月の距離が近いときに起きる満月が、スーパームーンと呼ばれます。
それでは、スーパームーンは、占い的にはどんな影響を及ぼすのでしょうか。
実のところ、占星術的にも、定義があるわけではありません。スーパームーンという言葉自体が、最近生まれたものだからです。
ただ、古い占星術には、「明るい光を放っている星は影響力が強い」というルールがあります。それに則れば、たしかに、スーパームーンは普段より明るさが大きいわけですから、特別な力を持っていると考えるのは、間違いではないでしょう。
しかも、満月は、月食になることもあります。2021年5月26日の皆既月食は、地球までの距離が約35万7000キロメートル。2021年12月19日のいちばん小さな満月と比べて、約5万キロメートルも近い位置で起こります。
2021年5月26日、スーパームーンの皆既月食が起きるのは射手座。
射手座の生まれの人には、なにか特別なことが起きるのかもしれません。
占いで使う暦・旧暦における、季節の分け目。
春夏秋冬の4回あるのですが、一般的に「節分」と呼ばれるのは、前年と今年との境目である「春の節分」です。
「節分の日」は、「立春の位置(水瓶座15度)に、太陽が到達する瞬間を含む日の前日」と定義されています。豆まきを行うのは、この日です。
毎年だいたい2月3日になることが多いのですが、2021年は2月2日です。なんと、1897年以来、124年ぶり。国立天文台の発表によれば、太陽が立春の位置に到達する瞬間が、2月3日23時59分(日本標準時)なので、このような日程になります。
また、立春の瞬間が2月5日になることもあり、1900年代の初めごろの節分の日は、2月4日になる年のほうが多いほどでした。2021年より先は、だんだん、2月2日が節分の日になる年が増えていきます。
なお、いわゆる「生まれ年の干支」や「九星
本命星」は、節分を境にして変わります。2021年は丑年(うしどし)・六白金星の年ですが、占いで使う暦では、節分の日まで前年の扱いです。すなわち、2021年2月2日生まれの子までは、子年生まれ、本命星は七赤金星となります。
※注
生まれ年の干支、九星本命星を決めるときには、さらに厳密に太陽の位置を勘案することもあります。同じ日付でも、太陽が立春の位置(水瓶座15度)に到達していなければ、前年として扱う占い師もいます。
【相生・相剋・比和(そうしょう・そうこく・ひわ)】:四柱推命/九星・気学/風水/算命学/易など
|
東洋の世界観のひとつ、「五行思想」では、この世界は、五行(木・火・土・金・水)が混ざり合ってできていると考えます。
五行は、少し複雑なじゃんけんのようなルールで、互いを助けたり害したりします。助ける作用は相生(そうしょう)で、一般的には吉、害する作用は相剋(そうこく)で、一般的には凶とされます。
■相生(そうしょう)
五行が変化して、互いを生み、循環する作用です。
木生火:木は燃えて火を生じる。
火生土:火は燃え尽きて土を生じる。
土生金:土は固まって金属を生じる。
金生水:金属は水を生じる(冷たく固まった金属の表面に水滴がつく)。
水生木:水は木を生じる(植物を発芽させ、育てる)。
→再び、木生火へと循環する。
たとえば四柱推命では、生まれた日の
十干の五行を見て、相性を占うことができます。
甲(きのえ)または、乙(きのと)の日に生まれた人は、木の日に生まれた人です。
木は、水から生まれます。すなわち、水である壬(みずのえ)または癸(みずのと)の日に生まれた人は、木の人にとって生んでくれる(恵みをもたらしてくれる)人で、ラッキーパーソンです。
また、木は火を生みます。すなわち、火である丙(ひのえ)または丁(ひのと)の日に生まれた人は、木の人にとって、育てたり助けたりしたい相手。愛情を注ぐ相手ですから、これも相性が良いということになります。
相生の関係が成り立つ人とは「相性が良い」と判定できますね。
■相剋(そうこく)
五行が互いを倒しながら、循環する作用です。
相手の力をそぐことを「剋す(こくす)」と言います。剋という字の中には、刀をあらわす「リットウ」が入っているのを見てもわかる通り、まさに刃物で一刀両断にして、相手を倒してしまうようなイメージです。
木剋土:木は土から養分を吸い取る。
土剋水:土は水を飲みこむ(乾いた地面に水がしみ込んで消える)。
水剋火:水は火を消す。
火剋金:火は金属を溶かす。
金剋木:金属でできた刃物は木を切り倒す。
→再び、木剋土へと循環する。
相生を説明したのと同様、四柱推命の相性を例にとりましょう。
木の日に生まれた人にとって、金である庚(かのえ)または辛(かのと)の日に生まれた人は天敵です。金は、斧。近づけば、木のように切り倒されてしまいます。
しかし、木の人にとって、土である戊(つちのえ)または己(つちのと)の日に生まれた人は、くみしやすい相手です。ともすれば、下に見たり、搾取したりしてしまう相手。
相剋の関係が成り立つ相手とは、加害者側になるにせよ、被害者側になるにせよ、あまり相性がよくないといえそう……。
■比和(ひわ)
五行のうちの一種類が並ぶことです。
生んだり剋したりすることはありません。量が増えれば、それだけ大きくなってパワーアップします。
ただし、東洋的な哲学では、五行のうちの一種類だけが大きくなりすぎるのは、よくないと考えます。
たとえば、火の最たるものは太陽。ほどよい力を発揮しているときは、恵みもたらす存在ですが、過剰に勢いが増すと、干ばつや自然火災が発生してしまうでしょう。
そのため、比和の関係は、吉とも凶ともいえません。
ほどよい分量なら気が合う相手、一緒にいて五行の一つばかりが肥大し、周りに迷惑をかけるなら、悪い仲間ということになるでしょう。